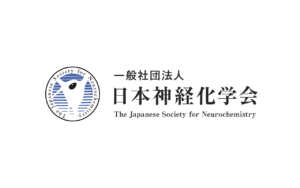私と神経化学「日本神経化学会」のルーツと歩み

御子柴克彦 (Katsuhiko MIKOSHIBA)
上海科技大学 免疫化学研究所教授
東邦大学理学部特任教授
日本神経化学会名誉会員
「日本神経化学会」は歴史的にみて世界で最初に創設された「脳の働きを物質レベルで解明する」ことを目指した学術団体である。脳の研究は色々な手法で行われていたが、物質を中心にして、脳の働きを物質レベルで解明しようとするNeurochemistry 神経化学による脳の研究が進められたが、国際的に日本が最初であったことは特筆される。
神経化学会のルーツ
「脳」という当時はまだまだ神秘的な対象であったが、それに対して「物質レベルでの解明」というある意味で革命的ともいえる思想的チャレンジでもあったと言える。日本神経化学会を立ち上げた先達はこのようなチャレンジをあえて行うという気概を持っていたと思う。私は慶応義塾大学医学部を卒業後、1973年に大学院生として生理学教室へ入室した。多くの人の興味の対象であった神経の伝達物質については、無脊椎動物であるザリガニではグルタミン酸が興奮性物質であり、GABAが抑制性物質であることは知られていた。しかし哺乳類のような脊椎動物と無脊椎動物も同様である保証がなく、むしろ両者では異なると考えられていた。
慶応医学部の生理学の林髞(はやし たかし)教授が哺乳類脳内でグルタミン酸が興奮物質であること(第二次大戦中1944年日本語、戦後1952年英文)、GABA が抑制性物質であることを世界で最初に示したことは大きな革命であった。また隣の生理学教室の冨田恒男(とみた つねお)教授が網膜の3原色説を1960年に証明されて3つの波長を吸収する異なる物質が色の感覚の認識を決めていることを示された。つまり主に文学部心理学教室で進められていた研究を物質レベルへと変革していた。
私と神経化学
私は林髞教授の後任の塚田裕三教授(日本神経化学を主導されていた中心メンバーの1人)の研究室に入室したが、脳の生理学的現象を物質レベルで解明しようという研究が進められており、私にとって大変に高揚感あふれる時代であった。更に私は大学院生の4年間のうちの後半2年間は慶応医学部の分子生物学教室(渡辺格(いたる)教授、春名一郎助教授)(生理学教室の隣の建物にあった)に学内留学していた。日本で医学部に最初に分子生物学教室が新設されたのは慶応医学部であったが、そこで私は分子生物学の還元論的考え方のシャワーを徹底的にあびた。
そのような時期を経て私は1985年から大阪大学蛋白質研究所に赴任して新しく研究室を立ち上げて「物質を求めての脳機能の徹底的な追求」、岡崎共同研究機構・基礎生物学研究所での「生物学を意識した脳へのアプローチ」(1986年〜1991年)と東京大学医科学研究所での「医科学、疾病と脳機能の関わり」(1991年〜2007年)などの研究を通じて様々な多様な経験をつむことができた。これらの時期に日本神経化学会の運営にも関わり、理事、大会長、理事長を仰せつかったが、上記の自分が重要であると信じていたことを学会運営に反映をさせて頂いた事は幸いである。
今私が思うことは、学問はフィロソフィーの上に成り立っていることをはっきりと認識しなければならない事である。一旦大きな発見がなされて、それの道筋に沿って研究が流れていくがその流れをさらに推し進める為の応用的な流れ, 応用に力をいれながら病気の克服に向かう方向、基礎研究に力をいれて予想外の大きな発見を求めて真理の探究を目指すなど様々である。どちらを我々は選択するかは個人によって考え方は違うと思う。1960〜70年代当時の日本神経化学会は脳の機能を物質的基盤で解明するという方向で、しかも機能を十分に意識しており、実際に心理学教室で行われていた行動学習も果敢に取り込んでいった。
日本神経化学会の歩み
当初は「日本神経化学懇話会」でありその後「日本神経化学会」と改名された(事務局は慶応医学部生理学教室にあった)。名前は「神経化学」であっても我々の頭の中には「脳科学」を研究しているという考え方をしていた。学会名は「脳科学会」でも良かったと思うが、今思うと当時の諸先生方は物質すなわち化学的に解明することの重要性を強く認識していた為に、「神経化学」にこだわり現在の名前となったと考える。
私たちは化学的研究手法と物質的基盤を理解するという大きな自信をもち「神経化学」の立場から「脳科学」の研究を大きく発展、生育していった。
理事長時代のキャンペーン
私が理事長に選出されてから(2001年〜2003年)いくつかのキャンペーンを行った。英語のヒアリング力を高めて多くの情報を取り込む事、また我々の情報を発信する為に英語での発表力を高めるというキャンペーンを行った。
しかし、私が特に強調したことは、「如何に日本オリジナルな研究を日本の研究室から生み出すか」にあった。私が強調したのは、考えることはきちんと自分の一番得意な言語(言語は文化であり、その文化の上にサイエンスをしようという考えを持っていた)で行うということであった。その為に、大会では母国語即ち日本語での発表をしても良いことにした。(しかし国際化も目指していたため聴衆に広く理解してもらうために、スライドやポスターは全て英語表記とした)。更に特徴あるのは日本神経化学会は当初から討論の時間を十分にとり徹底的に討論することを目指していた。発表時間15分に15分の質疑応答時間を準備した。
日本神経化学会は物質を意識した生化学、生物物理、分子生物など物質レベルでの実質的な議論が会場では強くなされているのが特徴である。
これは学会の演題数が多い少ないの問題ではなく、学会をどのように運営していくか、特にどのように、どのような討論を進めて行くか、討論の中からどのような新しい考えを生み出していくかが重要であり、それに関しては日本神経化学会は十分にその役割を果たしてきたし、現在もしていると思う。
更に神経化学会では他学会に比べて若手の教育を重要視していた。若手の育成をすることが研究者に必須という考えの下に「若手育成セミナー」を開催して先輩からの体験や考え方などを直接に聞けるセミナーの開催をきめ細かく、着実に行われている。この「若手育成セミナー」の講師も2度程お引きうけしたが、熱気は凄まじいものである。とくに大学院へ入るか否か、などの進路相談など多い。研究者を目指す若手が聴講して、しばらくするとそこから育って来た人が講師をつとめるという良い流れが生まれているように思う。大きな成果をあげていると思う。
「日本神経化学会」と「日本神経科学学会」の関わり
一方、日本神経科学学会の設立のきっかけはIBROの国内加入団体として整備した「日本神経科学協会」が 前身になっている。日本神経化学会とは設立のフィロソフィーにおいて大きな違いがあった。
さて具体的に学会を進めていく上で「神経科学学会」との連携のスタンスをどのようにするかが大きな問題であった。当時は「日本神経化学会」の方が「日本神経科学学会」よりも会員数は多かった。しかし、私が理事長をしていたときに脳の研究を更に大きくすすめる為には「神経化学会」と「神経科学学会」との連携を強くしていく方が良いと考え、私から神経科学学会へ申し入れをして、神経化学は私が大会長として、廣川信隆教授が科学の大会長として第一回の合同大会を開催した。設立のフィロソフィーが違う両学会ではあるが、それぞれの学会のフィロソフィーを尊重しつつ、定期的に合同大会が開催されている。
現在私は海外に研究と教育拠点を移したが、研究はヒトがするものであり、その研究をするヒトの育成は非常に重要である。科学における真実は国を超えても、宗教が違っても文化が違っても共通である。これまでの経験を生かしながら次世代の研究者育成にしばらく力を注ぎたいと考えている。頻繁に日本に戻っているので(東邦大学理学部特任教授を拝命している)日本と中国の交流にも力をいれていきたい。
これから日本神経化学会は基礎研究を基礎におきながら、予想外の大発見をしながら、得られた基礎的な研究成果を応用研究へと更に大きく展開するように進んで欲しい。日本の神経化学研究が今後益々ユニークな形で大きく発展され世界をリードされることを心よりお祈り申し上げたい。
(2020年2月 原稿受領)