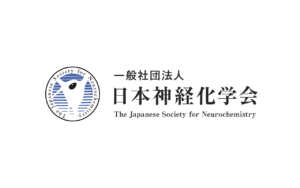私と神経化学

組織化学との出会い
私が医学部を目指したのは医師になりたいということではなく、脳の研究をしてみたいというのが動機である。入学した当時は紛争真っただ中。時間は十分にある。部活の卓球、今話題の麻雀、学生運動三昧、それに加えて研究を覗いてみたくなる。当時の阪大には業室研究員という制度があり、学生は希望する研究室で研究の真似事ができるようになっていた。そこでどの研究室を選ぼうかと悩んだのである。阪大には高次神経研究施設というのがあり3部門からなっていた。神経薬理生化学は佐野勇先生、神経生理は岩間吉也先生、そして解剖は清水信夫先生である。脳は100ミクロン異なれば違う細胞集団。脳をすりつぶして研究するのはどうか、電気生理は局所すぎるし、などと生意気に解析。清水先生のところでは脳内アミンを切片上で可視化。組織化学の先立ちである。「これや!」と先生の門をたたき、国家試験の直前まで入り浸り。おかげで卒業試験の面接では「君は基礎へ行くようやな」と別待遇で。
1972年医学部を卒業後、すぐに助手にしてもらい、脳内アミンの研究に。そしてフランスに招聘。ただその間、アミンニューロンは脳のごく少数の細胞集団で、脳の主たる機能はアミン以外の伝達物質で制御されていることが次第に確立し、それではその伝達物質は何か?という競争が始まる。1970年代のことである。
免疫組織化学、in situ hybridizationへ
そこに浮上してきたのが神経ペプチド。フランスから帰国後助手の身でありながら、教授空席のラボを任され、何を研究の主体にするか迷っていた折にちょうど出会ったのが塩坂貞夫先生(奈良先端名誉教授、大阪精神医療センター)である。そんなつぶれかけのラボではあったが、意欲だけは意気軒高。当時はやりのHRPを用いた線維連絡に走るか、Golgi法などの形態学の本道を歩くか、神経ペプチドを扱うか、など方向性についてアルコールも入りながらの議論。結局、未開拓の神経ペプチドをメインにしようと。そうなると、未知のペプチドを見つけるか、当時開発され始めた免疫組織化学で神経ペプチドの脳内網羅解析から機能を導くかである。前者への思いは強かったが、我々の実力からして後者の選択となる。そうなると抗体の取得、手技の向上がキーである。市販の抗体はイムノアッセイ用で、形態学には向かない。そうなると抗体を何処からか、入手せねばとなる。そんな折、ある抗体をもらって共同研究をしていたラボから、この研究論文は自分のところをトップにしたいという申し出が。アイデアと労力はこちら、当然激怒である。この共同研究はなしということに。その時感じたのは、やはり「エエ抗体を自分のとこで作らねばあかん」ということ。この事件がきっかけとなり、我々は自前の抗体をそろえることとなる。ただそれに必要な抗原は高価。バイトなどの上納金で賄う。今なら、なんと言われるだろうか。それぞれが自分のやりたいペプチドの解析が始まる。仙波恵美子先生(和歌山医大名誉教授)、稲垣忍先生(阪大名誉教授)、島田昌一先生、木山博資先生、吉田成孝先生、和中明生先生,田中潤也先生などの面々の昼夜を分かたぬ努力(たこ部屋)が身を結び、スウェーデングループと肩を並べる評価を得た。しかし、時代は蛋白から遺伝子へと流れていた。そこで塩坂先生、木山先生の遺伝子可視化の努力が始まる。幸い1985年、阪神が優勝した年、私が別の講座(解剖学第二講座)を主宰することとなる。彼らが新たに参加した野口光一先生や佐藤康二先生、佐藤真先生らの努力で高感度のin situ hybridization法が。これで蛋白から遺伝子までの組織的解析が可能に。教室も大盛況となる。しかし依然として残るわだかまりが、自分たちのオリジナルな分子を持ちたい、という気持ちである。我々の役割が、いわゆる「染め屋」としての役割ならば、あまりにも悲しい。
大阪大学医学部最初の寄付講座が神経化学への道を切り開く
神経化学へ舵を切るきっかけとなったのは、田辺製薬千畑一郎社長(当時)との出会いである。「田辺の中枢研究の主体は先生に任せます」というお言葉をいただき(ただし、代替わりになってこの言葉は反故に)、医学部に初の寄付講座を作ることとなった。1996年のこと。製薬会社の研究の基本は分子を扱う。まさに願ったりかなったりである。設置をめぐる教授会での論議では企業の手先の様な発言もあり、多くの叱責を受けたが、時がたち、今は昔、今や寄付講座はごく普通の産学共同形態となった。ただ寄付講座の精神は大きく変貌している。今の寄付講座は臨床系統が主体であり、ややもすれば、他学で十分活躍できる人材を教授が自分の勢力内に囲い込むために用いられるふしもあるが、それは本末転倒である。寄付講座は大学が持たないもの、企業が持たないものを融合させて、幅広い視野と手法を持つ人材を育成することにある。医学部初の寄付講座は我々に大きな財産を残してくれた。我々が持たない分子生物学的手法を我々に植え付けたのである。かくして我々のグループでは「自分の持つ手法から研究テーマを選ぶのではなく、研究内容から手法を選ぶ」という我々の信条が確立した。それと共にこの寄付講座には臨床からの参加者も多く、人材育成の宝庫となった。今泉和則先生、片山泰一先生(いずれも田辺製薬から基礎研究へ)、堀修先生、山下俊英先生、鵜川眞也先生、五味文先生、宮田信吾先生、森泰丈先生、秦龍二先生、金銅英二先生、工藤喬先生、板東良雄先生など神経化学会で活躍の先生方を多数輩出した。我々が形態学と神経化学を手にしたことから、我々の研究は自分たちの分子を軸に、小胞体ストレス、痛みの分子機序、神経再生の分子機序、統合失調症、うつ病、自閉症の分子機序と助教授が旅立つとともに研究分野が広がっていった。その意味で病気と機能を軸とした解析には神経化学が不可欠ともいえる。
最後に
研究の現場から退いて10年近くなる。神経化学、あるいは神経科学の研究にいそしむ研究者を見ていると「脳科学者の脳知らず」という感を持つときがある。ほんの局所のことですべてを語るのは危険である。神経解剖の基本的知識の上で、機能、作用を論議してほしい。あなた方の努力が歴史から見て砂上の楼閣とならぬように。
(2020年6月原稿受領)