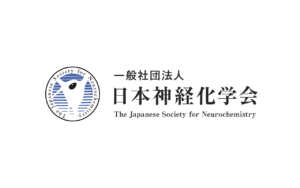委員長だより( 脳研究推進委員会 )
小泉理事長主導のこの委員長だよりも、毎回第三者的に楽しませていただいて来ましたが、ついに自分が最終回として書くことになりました。日本にもCOVID-19が襲来し、毎度マスクをして外出するようになってから1年になります。日々の報道も、我が国では、コロナとオリンピックばかりで、多くの方々の関心も兎角そちらに行きがちですが、コロナによる二次被害として、我が国の少子化には拍車がかかり、認知症や心の病の問題は、確実に深刻さを増しています。現在、我が国では十分な対策が取られていると言えるでしょうか?また、コロナ禍に直面して露呈したことではありますが、デジタル化をはじめとする様々な制度の脆弱性も指摘されています。この様な劣勢から、我が国は、巻き返しをはかることはできるのでしょうか?
医学・生命科学に目を向けてみますと、不思議なことに日本よりコロナ禍が悲惨で、行動制限も、より厳しい国々から、毎日のように華々しい研究成果が発表されています。この厳しい状況下でも成果を発表し続けるためには、何が要因となっているのか?Withコロナ、Afterコロナで、我が国は、学問の世界でリーダーシップを発揮できるのか?本学会で取り組むべきことは何か?などつらつら考え、メールベースでの脳科学推進委員会で議論を行いました。委員の皆様(尾藤 晴彦、竹居 光太郎、澤本 和延、林-高木 朗子、林 真理子、田中 謙二、望月 秀樹、加藤 忠史、小野 賢二郎、和田 圭司、小泉 修一:敬称略)からいただいたご意見を整理・統合して、そのエッセンスを以下にまとめてみました。
脳科学連合, 脳科学委員会における本学会の立ち位置:
神経化学こそが、先端神経科学と最新脳神経医学の接点であり、あらゆる脳科学のブレークスルーの中核に位置すべき学問分野であります。現在ほど、神経化学に基づき、精神・神経疾患の病態を解明し、根本治療戦略創出に貢献できる時代はなかったといえるのではないでしょうか?
換言すれば、分子・物質からみた脳科学が本学会の最たる特徴の一つであることから、新たな分野との融合を行う場合においても、システムやAIへの融合へと進む他の学会とは異なる視点で他分野との融合を目指す展開、つまり分子基盤に立脚した考えが前面に出る研究展開として、生物学的な脳機能の解明においても、病因解明においても、プレシジョンメディシンを見据えた治療法開発においても、分子=標的の特定化が優先された考え方で考究することが本学会の立ち位置であります。平たく言えば、本学会は、基礎も臨床もどちらも強く、扱う範囲が広いというのは、学際性の基盤になるので、大きな強みになるでしょう。
その一方、日本の人口が減り、研究者の数が減る中で、日本の脳科学そのものが危機に瀕しています。これは、世界的な傾向でもあり、SfN (Society for Neuroscience)でも参加者が減り始めており、脳科学関連領域が結束しないと、だんだん苦しくなっていくと思われます。乱立する国内学会のどこかが一人勝ちすることはもはや無理で、いろいろな意味で結束すべきであります。現在の脳科学連合は、その役割を十分に果たしているのかは、さらに見直しが必要であると思われます。その中で、基礎にも、臨床にも強い本学会は、扇の要の役割を担っていくべきものと考えます。
我が国の脳科学関連学会の中において本学会が優れている点の一つとして、国際的な優位性があります。本学会は世界で最初に作られたNeurochemistryの学会であり、会員数も多く、2022年に国際神経化学会(ISN)を京都で開催することで、さらにその優位性が高まることが期待されます。
文部科学省・脳科学委員会やAMEDでの脳科学の動向と本学会での取り組み:
2020年度からのAMEDの新体制では、医薬品、医療機器・ヘルスケア、再生・細胞医療・遺伝子治療等6つの統合プロジェクトを中心とする研究開発を推進するといういわゆるModality別の立て付けへと体制変更が行われ、「脳と心」という重点領域としてのキーワードが消失しました。古くは伊勢志摩G7サミットで提言された「脳研究の推進」が、今後人類が直面する高齢化社会において解決すべき課題の一つとして注目されてきましたが、この度脳科学というキーワードがなくなったのは、脳科学という分野に特化した研究を推進することが、もはや先進性に欠け、その一方他分野との融合などから見出される新たな展開の必要性が高まったことが、この背景にあるのではないかと考えらえています。
この様な状況を踏まえて、AMEDの「脳と心」という重点領域としてのキーワードが消失した事につきましては、ピンチと捉えるか、チャンスと捉えるかという両面からの議論が行われました。
ピンチとして捉える考え方として、やはりAMEDで「脳と心」がなくなったことが、ボディーブローのようにだんだん影響してくることが心配されています。もはや脳科学というだけではお金がもらえず、他の領域と戦っていかねばならないということになリます。また、今回、脳科学は疾患基礎研究という枠に入れて貰っていますが、この名前も、これまでの基礎臨床融合という方向性に逆行するものであると考えられます。脳科学はモダリティーを超えた研究が重要であり、基礎と臨床の融合が特に必要な領域であるということをアピールしていかねばならないでしょう。
一方、心強いことに、チャンスと考えている方も少なくありません。脳科学というキーワードが消失したのは、決して脳科学が下火になったのではなく、脳科学は生命科学の基礎学問になったものと解釈できます。意識、自我、愛憎などの大きなquestionは横たわったままであり、脳科学の学問としての面白さに変わりはなく、今後は脳科学だけでなく他分野や様々な科学技術と融合した統合的な「Global Science of Brain」として、まさに『ライフサイエンスのための脳科学』を提唱していくことが今後の戦略となるのだと考えられるのではないでしょうか?
やはり、チャンスは、ピンチの顔をしてやってくるようですね。その意味でも、本学会としての取り組みを戦略的に取り組む必要があるでしょう。
Withコロナ, Afterコロナに於いて、神経化学会のプレゼンスを増す為には?:
コロナ禍で、学会の意義が問われています。大会がon line化されている中、新しい人と出会う機会が少なくなっており、既に知り合いが多い研究者はWebだけで事足りる面もありますが、研究を始めたばかりの人にとっては、Informalなコミュニケーションが少ないことのマイナス面が多いと思われます。その為には、新入会員をサポートすることができれば有意義と思われます。
他学会を見てみますと、海外では、国際精神科遺伝学会(World Congress on Psychiatric Genetics)では、Early Carrier Investigator Support Programといった、若手の希望者にメンターがつくシステムがありますし、国内では日本神経学会の将来構想委員会では、創薬の神経内科の若手のための勉強会やバイオインフォマテイックスハンズオンも開催しています。神経化学会も、疾病からの創薬という流れを強調して、総会以外のイベントを組んで学会の存在意義をアピールすることが重要だと思います。また、本学会が今後も取り組むべきは人材の育成であります。学問も、交流も、excursion(飲み会、テニス)も、学生を巻き込んで皆で楽しむことで下が育つのではないでしょうか?
慶應義塾大学の田中 謙二さんは、「私はそうやって育てられた。本気で遊ぶヒトが減ってきたので、今こそ、本気で遊ぶべきだと思います。遊びの内容は人それぞれで良く、楽しむことです。研究も遊びです。これは決して不謹慎な発言ではなく、皆さんも研究は究極の遊びだと思っているはずです。」と述べられていましたが、私も100%この考えに賛成です。コロナという全世界的な脅威が発生しますと、それは進化に少なからず影響を与えます。進化の過程で生き残った生物は、決して最強の生物ではなく、環境の変化に適応できた生物です。コロナの影響で、どのように進化するか、最も影響を受けるのは、生物というより、REAL WORLDでは学会であり、企業であり、大学ではないでしょうか?
遊ぶ余裕のある学会こそ、進化し、生き残れるものと確信しております。
緊急事態宣言下、我が国の新規コロナ感染者数も次第に減りつつはありますが、なかなか台湾や中国のレベルにはなりませんし、ワクチン接種もなかなか苦戦している中、東京オリンピックをどうするのか?といった大事なことが決まらない不安定な状況が続いています。ただ、こんな状況こそ、本学会が進化する大きなチャンスを抱えているのではないかと思っております。
脳研究推進委員会委員長
岡野 栄之
(2021年2月21日)